退職を考えている人必見!退職手続きに必要なものと流れ~スムーズに進めるポイント~
いいね
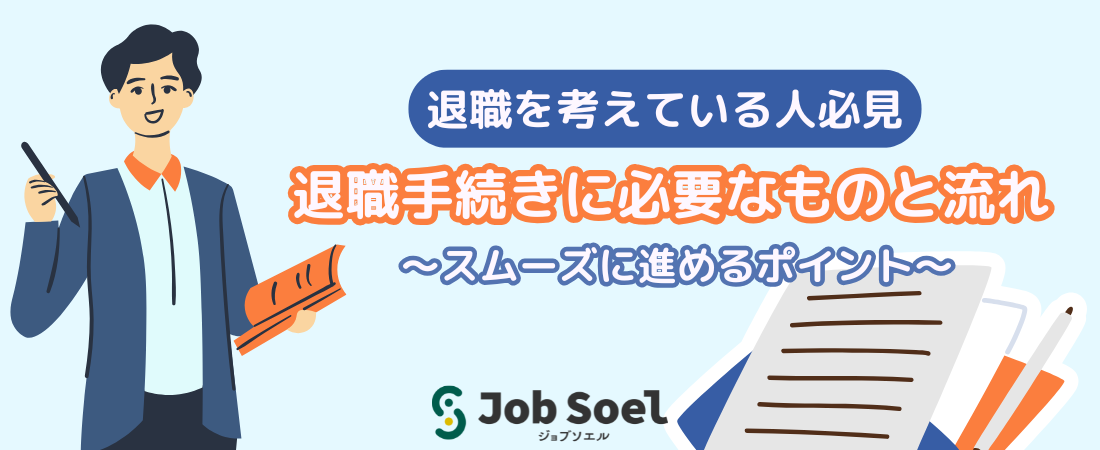
「退職したいけど、何から始めればいいのだろう?」
忙しい医療・介護業界で働く皆さまにとって、退職を考えることは決して簡単な決断ではありません。
患者さまや利用者さま、同僚への配慮も必要ですし、引き継ぎや手続きの準備に手間取ることも多いでしょう。
しかし、適切な準備をしておけば、退職手続きはスムーズに進められます。
本コラムでは、医療・介護業界に特化した退職手続きの流れと必要なものを解説します。
以下の内容を参考に、負担を減らしながら次のステップに進む準備を整えましょう。
目次
1.退職の意思表示のコツとタイミング
退職を考えるとき、最初のハードルは「いつ、どのように意思を伝えるか」です。
「退職の意向を伝えるのが気まずい」と感じる方も多いのではないでしょうか。
医療・介護業界の忙しい現場では、突然の退職が職場や患者さまに与える影響が大きいため、慎重な対応が求められます。しかし、適切なタイミングと方法を選べば、円満退職への道が開けます。
① タイミングを見極める
退職の意思を伝えるタイミングは、一般的に1〜3ヶ月前が望ましいとされています。この期間は、職場が引き継ぎや後任者の手配を進めるために必要な時間です。
また、就業規則や雇用契約書に退職の予告期間が記載されている場合は、その内容を確認しておきましょう。
一方で、民法第627条では、期間の定めのない雇用契約の場合、労働者は退職の申し入れを2週間前に行えばよいと明記されています。
法律上は2週間前でも退職は可能ですが、職場の状況を考慮して余裕を持ったタイミングで相談することをおすすめします。
② 退職の伝え方
退職の意思は、直属の上司に直接伝えるのが基本です。その際、退職理由を深く説明する必要はありません。「一身上の都合で」と簡潔に述べるだけで十分です。
もし転職先について質問された場合も、答える義務はありません。自分が話したい範囲で簡潔に伝えましょう。
医療・介護業界特有の課題として、人手不足の中で退職を申し出ると引き止められる可能性があります。
「現場が回らない」といった理由で辞めづらい雰囲気が生まれることもありますが、退職の自由は労働者の正当な権利です。自分の意思を明確に持ちながら、職場への配慮も忘れずに進めましょう。
2.退職日の決定と有給休暇の調整
退職日を決める際には、個人の都合だけでなく職場の状況や法律、社会保険の仕組みも考慮する必要があります。また、有給休暇の消化も含め、計画的に進めることが大切です。
① 退職日を決める際のポイント
-
入社日の前日を退職日に設定する:
次の職場が決まっている場合、退職日は入社日の前日に設定するのが最適です。このスケジュールであれば、国民健康保険や国民年金に切り替える必要がなく、健康保険や厚生年金保険の継続がスムーズです。 -
繁忙期や人事発令を避ける:
医療・介護現場では、繁忙期や特定のタイミングでの退職が現場に大きな影響を与えることがあります。患者さまや利用者さまへのケアを最優先に考え、繁忙期を避けることで職場への配慮を示しましょう。
4月や10月の人事発令前に退職を申し出れば、欠員を考慮した異動計画が立てやすくなります。 -
社会保険料の仕組み:
退職日が月中の場合、その月の社会保険料は発生しません。一方、月末に退職した場合、その月分の社会保険料も支払う必要があります。
ただし、再就職まで1日でも空く場合は、国民年金や国民健康保険への加入が必要になります。これらを考慮し、退職日を計画的に選びましょう。
② 有給休暇の消化
-
労働者の権利としての有給休暇
労働基準法第39条に基づき、労働者には退職前に有給休暇を取得する権利があります。退職日までに残りの有給休暇を計画的に消化することで、最後まで余裕を持った退職準備が可能です。 -
上司との話し合い
職場の人手不足や業務量を考慮しながらも、自分の権利をしっかり主張しましょう。具体的なスケジュールを事前に共有することで、スムーズな調整が可能になります。
③ 賞与と退職金の確認
-
賞与のタイミング
賞与(ボーナス)は退職時の大きな金銭的要素のひとつです。支給日を確認し、必要に応じて退職日を調整しましょう。 -
退職金の支給条件
退職金の支給には勤続年数などの条件が定められている場合が多いです。条件を満たさないと支給対象外になる可能性があるため、事前に退職金規定を確認しておきましょう。
3.退職届の提出とフォーマット
①退職願と退職届の違い
退職願は、退職の意思を職場に伝えるための書類です。
退職の意思が確定していない場合や、まだ相談の段階で使用されることが多く、提出後に撤回できる可能性があります。
「これから話し合いを進めたい」という意図を示す際に適しています。
一方、退職届は、退職日が確定した後に正式に職場へ通知するための書類です。一度提出すると撤回が難しく、職場が退職手続きを進めるための基礎となります。
「正式な意思表示」としての役割を果たすため、提出時期や内容に注意が必要です。
②退職届を提出するタイミング
退職を進める際、「退職の意思を伝えるタイミング」と「退職届を提出するタイミング」の違いに戸惑う方も多いかもしれません。
退職届は、退職の意思を上司に伝え、退職日などが確定した後に提出するのが一般的です。
相談の前に提出してしまうと、一方的な通知と受け取られ、上司や職場との関係に悪影響を与える可能性があります。
そのため、まずは上司に相談し、話し合いを経た上で正式に提出するようにしましょう。
ただし、以下のような状況では、退職の意思を伝えると同時に退職届を提出する場合もあります。
-
明確な退職理由がある場合(家庭の事情や転職先が決まっている場合など)には、同時提出が問題ないケースもあります。
-
勤務先の規定で同時提出が求められる場合もあるため、事前に就業規則を確認しましょう。
同時提出を求められる場合でも、事前に上司に相談する姿勢を見せることで、職場との円満な関係を維持しやすくなります。
③書類の準備と作成方法
退職届を作成する際は、以下のポイントを押さえましょう。
-
勤務先で指定のフォーマットがある場合
総務部や人事部に確認し、指定の形式があればそれを使用してください。 -
指定がない場合
シンプルな形式で問題ありません。以下は一般的な退職届の例です。
手書きや捺印が必要な場合もあるため、事前に勤務先のルールを確認しておくと安心です。
また、退職理由は「一身上の都合」と記載するのが一般的で、詳細を記載する必要はありません。
④提出方法と注意点
退職届の提出は、退職日の約1ヶ月前を目安に行うのが一般的です。これにより、職場が引き継ぎや人員補充を円滑に進めるための時間を確保できます。
提出は、直属の上司に直接手渡しするのが基本です。メールや郵送では形式を欠くと捉えられる場合があるため、できる限り対面で渡しましょう。
提出時には、「これまでお世話になりました」「最後まで引き継ぎをきちんと行います」といった感謝や誠意を伝えることで、円満退職につながります。
4.業務の引き継ぎ
退職時の業務引き継ぎは、職場や患者さま・利用者さまへの影響を最小限に抑えるために非常に重要です。
特に医療・介護業界では、患者さまや利用者さまのケアが途切れないよう、正確で丁寧な引き継ぎが求められます。
①引き継ぎ準備の基本
業務引き継ぎをスムーズに行うためには、事前準備が欠かせません。以下の点を押さえましょう。
-
担当業務の整理
担当している業務をリスト化し、重要なタスクや継続が必要な業務を明確にします。特定の患者さまや利用者さまのケア内容、進行中のプロジェクトなども整理しておきましょう。-
曜日ごとのルーティン業務
-
特定の患者さまのケア内容
-
チームで進行中のプロジェクトの進捗状況
-
-
重要情報の補足と共有
治療方針、注意事項、家族との連絡状況など、業務に必要な情報を正確に共有します。特別な配慮が必要な点や細かなニュアンスについても記載しておくと、次の担当者が業務をスムーズに進めやすくなります。-
夜間に不安が強まる患者さまへの対応方法
-
家族からの定期的な報告依頼の背景情報
-
最近の治療方針変更や家族の同意状況
-
-
データや書類の整理
必要な書類やデータの保管場所を明確にし、次の担当者がスムーズにアクセスできるよう準備します。個人的に管理していたメモやファイルも、必要であれば共有・整理しておきましょう。
②引き継ぎの進め方
引き継ぎは、ただ情報を渡すだけでは不十分です。次の担当者が業務をスムーズに開始できるよう、以下のポイントを意識しましょう。
-
重要事項を優先して共有する
業務全体を網羅するよりも、緊急性の高い対応や重要なタスクに焦点を当てて引き継ぎを行います。これにより、次の担当者が初日から円滑に対応できるようになります。 -
現場での引き継ぎとフォローアップ
書類やデータの共有だけでなく、必要に応じて現場で一緒に業務を行いながら引き継ぎを進めます(OJT形式)。質問の時間を設けたり、引き継ぎ後に疑問を解消できる場を用意することも有効です。
③引き継ぎのメリット
適切な引き継ぎを行うことで、以下のようなメリットがあります。
-
ケアの質の維持と次の担当者の負担軽減
必要な情報を正確に共有することで、患者さまや利用者さまへのケアが途切れることなく継続され、サービスの質を維持できます。また、整理された引き継ぎ内容は次の担当者の業務負担を軽減します。
職場との円満な関係の維持
丁寧な引き継ぎは、職場への感謝や誠意を示す行為でもあります。これにより、退職後も職場との良好な関係を保ちやすくなり、トラブルの回避にもつながります。
5.退職時の手続きに必要なもの
① 退職時に勤務先へ返却するもの
退職時には、勤務先から貸与された物品をすべて返却する必要があります。以下の項目について、漏れがないよう注意しましょう。
-
健康保険証
健康保険証は退職日までに勤務先へ返却する必要があります。退職日以降は使用できないため注意してください。家族分(被扶養者分)も忘れずに返却しましょう。 -
名札や鍵、職員専用物品
施設内で使用していた物品(名札、制服、バインダー、セキュリティカード、ロッカーの鍵など)はすべて返却します。施設ごとに返却リストが異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。 -
貸与された医療器具やIT機器、システムアクセス権
医療現場では、業務で使用するために貸与されている器具や機器があります。例えば、聴診器やタブレット端末などが該当します。退職時には使用状況を確認し、漏れなく返却してください。
また、患者情報管理システムや電子カルテなどのログイン権限についても注意が必要です。退職後にアクセス権が残ると情報漏洩のリスクがあるため、退職時に施設側で権限解除の手続きを依頼しましょう。
② 退職後に受け取る書類、退職金について
退職手続きに必要な書類は、退職時または退職後に勤務先から受け取るものが多くあります。これらは転職先での手続きや公的な申請に欠かせないものです。
以下のリストを参考に、漏れなく確認してください。
-
雇用保険被保険者証
雇用保険の加入手続きや失業保険申請に必要な書類です。勤務先で保管されている場合は、退職時に必ず受け取りましょう。紛失している場合は、ハローワークで再発行が可能です。 -
年金手帳
年金関連の手続きで使用します。勤務先が保管している場合は返却を受けてください。個人で管理している場合も、所在を確認しておくと安心です。 -
健康保険資格喪失証明書
加入していた健康保険を脱退したことを証明する書類です。転職先での社会保険加入や国民健康保険への切り替え時に必要となります。通常、退職後数日~2週間程度で発行されます。 -
離職票
失業給付を申請する際に必要な書類です。退職時、職場に希望を伝えることで発行手続きが行われます。発行までに時間がかかる場合があるため、必要な場合は早めに申請しておきましょう。 -
源泉徴収票
年末調整や確定申告で使用する重要な書類です。退職後に郵送されることが一般的なので、忘れずに受け取って保管してください。 -
退職金の明細書・最終給与明細
退職金が支給される場合、その明細書を受け取ります。また、退職月の給与明細も後日送付されることが多いです。これらの書類は税務手続きにも必要になる場合があるため、大切に保管してください。 -
勤務証明書(必要な場合)
転職先で勤務実績を証明する書類が求められることがあります。その場合、施設に依頼して発行してもらいましょう。早めに申請することでスムーズな対応が可能になります。
退職後の手続きに必要な書類は多岐にわたります。各書類の用途を把握し、受け取り漏れがないように計画的に進めましょう。
6.退職後に必要な手続きと次のステップに向けた準備
退職後は、社会保険や失業給付などの公的手続きを進める必要があります。加えて、転職活動を見据えた準備を行うことで、次のキャリアをスムーズにスタートさせることができます。
① 健康保険の切り替え
退職後の健康保険には以下の3つの選択肢があります。自身の状況に合った方法を選び、早めに手続きを進めましょう。
-
任意継続被保険者制度
退職前に加入していた健康保険を最長2年間継続できる制度です。ただし、保険料は全額自己負担(退職前の約2倍)となるため、事前に確認して選択してください。退職日翌日から20日以内に、協会けんぽや健康保険組合に申請書を提出する必要があります。 -
配偶者の社会保険に加入
配偶者が会社員または公務員の場合、その扶養に入ることで健康保険料の負担を避けることができます。収入などの条件を満たす必要があるため、配偶者の勤務先に確認し、必要な手続きを進めましょう。 -
国民健康保険への加入
自営業や無職の方が加入する保険です。保険料は前年の所得を基に計算されます。退職日翌日から14日以内に市区町村役場で手続きを行ってください。
② 年金の手続き
退職後は、厚生年金から国民年金に切り替える必要があります。以下のいずれかに該当するかを確認し、適切な手続きを行いましょう。
-
国民年金第1号被保険者
自営業や無職の場合、個人で年金を納付します。市区町村役場での手続きが必要です。 -
国民年金第3号被保険者
配偶者が厚生年金や共済年金に加入している場合、その扶養に入ることで保険料の負担を回避できます。配偶者の勤務先を通じて申請を行いましょう。
③ 失業給付の申請
次の職場が決まっていない場合は、失業給付を活用することができます。申請手続きは最寄りのハローワークで行います。以下の書類を揃えて申請してください。
-
離職票
-
雇用保険被保険者証
-
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
-
印鑑
-
振込先口座の通帳またはキャッシュカード
所定の手続きを経て失業給付が開始されます。
7.スキルアップから次のステップへ
退職後の時間を有効に活用し、自分のスキルアップに取り組むことは、次のステップをより充実させるための重要な準備です。
特に医療・介護分野では、新たな資格やスキルを取得することで、転職活動を有利に進め、自身のキャリアを広げることができます。
① スキルアップのポイント
医療福祉分野の資格(介護福祉士、ケアマネージャーなど)に挑戦することで、専門性を高められます。
また、専門学校やオンライン講座を活用すれば、隙間時間を効率的に活用することが可能です。
さらに、チームリーダーや施設運営を目指す場合は、マネジメントスキルを学ぶことで役割を広げることができるでしょう。
スキルアップは、転職活動の選択肢を増やすだけでなく、次の職場での活躍の可能性を高める大切な一歩となります。
8.転職活動とJobSoel(ジョブソエル)の活用
スキルアップと並行して、次の職場探しにも取り組んでみましょう。
医療・介護分野での転職には、専門の求人情報プラットフォームであるJobSoel(ジョブソエル)の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
JobSoelでは、全国の医療福祉に関する職種の求人情報を検索できるほか、施設の雰囲気や具体的な取り組みを知ることができます。
新しい職場での働き方や成長のチャンスを具体的にイメージしながら転職活動を進められるので、安心して検討できますよ。
自分に合った職場を見つける一助として、ジョブソエルを活用してみてください。効率的に転職活動を進めるための心強いツールとなるでしょう。
▼求職者様_会員登録ページ
https://jobsoel.com/sign-up
▼企業・法人様_会員登録ページ
https://jobsoel.com/company-sign-up
9.まとめ
退職の準備は、次のステップへ進むための大切なプロセスです。
本コラムでは、退職の意思表示や有給休暇の調整、退職届の提出など、基本的な流れを解説しました。
また、退職後に必要となる社会保険や年金、失業給付の手続きについても触れました。
こうした準備を整え、手続きや引継ぎをスムーズに行い、その後の生活や新たな選択肢に向けて、安心して次の一歩を踏み出しましょう。
