介護記録の意義と効果的な書き方:現場でのスムーズな情報共有とケア向上を目指して
いいね
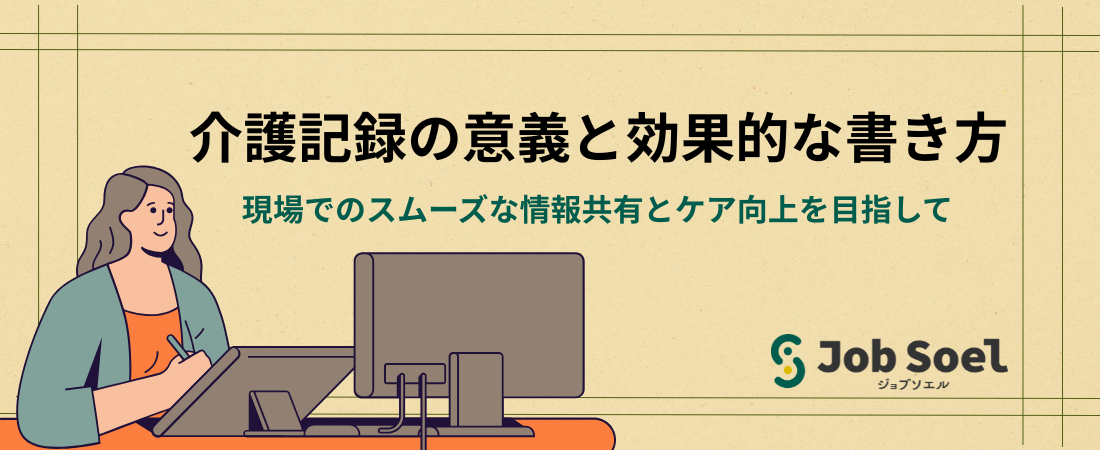
介護職に従事していると、日々欠かせない業務のひとつが「介護記録」です。介護記録は、利用者の健康状態や提供したサービスの内容を共有し、最適なケアを実現するための大切な記録です。
しかし、介護職に就いたばかりで「記録を書いてください」と言われても、どこから手をつけていいのかわからず不安を感じる方も多いのではないでしょうか。施設によってはフォーマットが決まっていることもありますが、必ずしもそうとは限りません。
また、忙しい業務の合間に、正確で効果的な介護記録を作成するにはコツが必要です。記録を書く目的や書き方のポイントを理解せずに取り組むと、情報が漏れたり不正確になったりすることもあります。
そこで今回は、介護記録の意義や書き方、効率的に記録を進める方法について解説します。ぜひ、参考にしていただき、介護記録に関する知識を深めてみてください。
1.介護記録とは
介護記録とは、介護職員が利用者に提供した介護サービスの内容や、利用者の状態を文字で残す記録です。介護保険法により、介護サービスの記録は義務づけられており、書き漏れなく記録することが必要です。
介護記録は利用者の身体的、精神的な状態を把握し、適切なケアを行うための重要な資料となります。また、介護サービスの実施内容は、後から振り返り、必要な情報を確認するためにも欠かせません。
日々の介護記録が漏れなく記録されることが、利用者の生活の質を維持するうえで大切です。
記録内容が端的すぎると、後から利用者の状態を適切に把握できず、重要な情報が共有されないこともあります。
したがって、まずは「介護記録を書く目的」を理解し、その意義を意識することで、より質の高い介護記録を作成することができます。
2.介護記録を書く目的
介護記録には、以下のような複数の目的があります。
-
職員間の情報共有
介護施設には、介護職員のほか、医師や看護師、リハビリスタッフなど多職種が関わっており、記録はこうした職員間で利用者の状態を正確に共有するための重要なツールです。職員が記録を通じて利用者の状態を把握することで、一貫性のある継続的なケアが可能になり、適切な対応が行われます。 -
ケアプランの作成と改善
介護記録は、現行のケアプランが適切であるかを確認し、今後のケアプランを作成・見直すための資料として活用されます。利用者の状態変化を正確に記録することで、必要に応じたケア内容の見直しが可能となり、より効果的なケアが実現します。また、日々の記録を通して提供したケアを振り返り、改善点を把握すること介護者で、介護サービス全体の質の向上につながります。
-
利用者・家族との信頼構築
介護記録をもとに、日々の介護内容や利用者の様子をご家族に詳しく伝えることができ、利用者やそのご家族に安心感を与えます。記録に基づく説明は、施設と利用者・家族間の信頼関係の構築に役立ち、より良いコミュニケーションが図れます。 -
トラブル時の証拠としての役割
万が一、利用者にトラブルや事故が発生した場合、介護記録は適切な対応が取られていたことを証明するための重要な資料となります。この記録は、利用者のためであると同時に、職員や施設を守る役割も果たします。正確な記録を通じて、介護者が適切なケアを実施していたことを示す根拠となり、法的な問題を回避する助けにもなります。
3.介護記録の書き方のポイント
次に、介護記録を適切に書くためのポイントを解説します。以下の点を押さえることで、わかりやすく、かつ正確な記録を残すことができます。
-
5W1Hを意識する
介護記録は、「Who(誰が)」「When(いつ)」「Where(どこで)」「What(何を)」「Why(なぜ)」「How(どのように)」の要素を基に構成することで、情報が網羅的に整理され、読み手に状況が伝わりやすくなります。特に主語を省略せずに書くことが大切です。
【例文】
良い例:「○月○日(When)、病棟A(Where)で□□さん(Who)が、食事中に誤嚥を防ぐため(Why)、体勢を高くして食事を取った(How)。」
悪い例:「病棟で□□さんの体勢を整えて食事を取ってもらった。」 -
公的文書として適切な文体・表現を使用する
介護記録は公的文書であるため、「です・ます調」ではなく「だ・である調」で統一し、簡潔に記載することが求められます。また、誰が読んでもわかりやすい具体的な表現を心がけましょう。
【例文】
良い例:「15:00、歩行訓練中に右足首の内側に軽い痛みを訴えたため、活動を中止し安静にした。」
悪い例:「午後の歩行訓練をしている時、右足が少し痛いと言っていたので、やめてもらいました。」 -
客観的な事実を具体的に記載する
介護記録には、介護者の主観や推測を入れず、利用者の行動や発言を具体的に記載することが重要です。主観的な表現や曖昧な記述を避け、観察した事実を客観的に記録することで、状況が正確に伝わり、他の職員が適切な対応をしやすくなります。
【例文】
良い例:「16:00、Aさんが廊下で立ち止まり、壁に手をついていた。『どこか痛いですか?』と声をかけると、『少しふらついたが大丈夫』と返答。痛みはないと話したため、近くの椅子に座ってもらい休憩した。」
悪い例:「廊下で不安そうに立っていたので、声をかけて休ませた。」 -
利用者の尊厳に配慮した思いやりのある表現を使う
介護記録は職員同士の情報共有が目的ですが、利用者やご家族が読んだ際にも配慮が感じられる表現が求められます。例えば、「徘徊」「不穏」「拒否」といった表現は、利用者の行動に否定的な印象を与える可能性があるため、「廊下を歩かれていた」「落ち着かない様子が見られた」といった柔らかい言い回しに置き換えるとよいでしょう。また、「~させた」といった指示的な表現も避け、「~を勧めた」など対等な立場からの表現にすると配慮が伝わりやすくなります。侮辱的な言葉や否定的な表現を避け、利用者の尊厳を大切にした記載を心がけましょう。
【例文】
良い例:「Bさんが『一人で歩きたい』と話し、廊下を一人で歩かれていたため、職員が見守りながら対応した。」
悪い例:「Bさんが廊下を徘徊していたため、職員が見守った。」
4.介護記録を効率的に進める方法
介護記録を効率よく進めるための工夫として、以下の方法を参考にしてみてください。
-
メモを取る習慣をつける
業務の合間に介護記録をまとめるのは難しいため、メモ帳を活用してキーワードや時刻を記しておきましょう。また、可能であれば1日の中で定期的に記録を書く時間を設けると、作業が溜まらず、情報の正確性も保ちやすくなります。 -
フォーマットの活用
食事、排泄、入浴など、日常的な場面に合わせたフォーマットや定型文を準備しておくと、記録作成が効率化され、読みやすくなります。施設に統一フォーマットがない場合は、職員間で相談して作成するのも良いでしょう。定型文(テンプレート)はあくまで基本形として、利用者のその日の状態や特別な出来事に応じて適宜調整し、柔軟に対応することも重要です。
状態や様子を表現する言葉をストックしておく
利用者の状態を正確に記録するため、皮膚の状態や顔色、呼吸の様子などの表現をあらかじめ準備しておくと便利です。例えば、「皮膚:赤みがある、黒ずんでいる、かさかさしている」「顔色:青白い、赤みが帯びている、土気色」「呼吸:ヒューヒュー(ゼイゼイ)と音がする、浅い、息が荒い」などの表現をストックしておくと、いざ記録を書く際に迷わずに済み、作業がスムーズになります。また、先輩や同僚の記録を参考に表現のバリエーションを増やすのも良い方法です。
5.転職活動とJobSoel(ジョブソエル)の活用
医療・介護分野での転職には、専門の求人情報プラットフォームであるJobSoel(ジョブソエル)の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
JobSoelでは、全国の医療福祉に関する職種の求人情報を検索できるほか、施設の雰囲気や具体的な取り組みを知ることができます。
新しい職場での働き方や成長のチャンスを具体的にイメージしながら転職活動を進められるので、安心して検討できますよ。
自分に合った職場を見つける一助として、ジョブソエルを活用してみてください。効率的に転職活動を進めるための心強いツールとなるでしょう。
▼求職者様_会員登録ページ
https://jobsoel.com/sign-up
▼企業・法人様_会員登録ページ
https://jobsoel.com/company-sign-up
6.まとめ
介護記録は、利用者の生活を支えるための重要な情報であり、職員間の連携やケアプランの見直しに欠かせない役割を果たします。
適切な記録を残すことで、利用者の健康状態を正確に把握し、迅速で適切なケアが提供可能となります。また、日々の記録を通じて、介護技術の向上や現場でのコミュニケーションの改善も期待できるでしょう。
現場では業務が多忙なため、介護記録の効率化を意識しながらも正確さを欠かさないことが求められます。
今回ご紹介したポイントを参考に、介護記録のスキルを高め、利用者の生活の質向上に貢献していきましょう。
