介護職の夜勤専従は大変?収入と働き方の実態
いいね
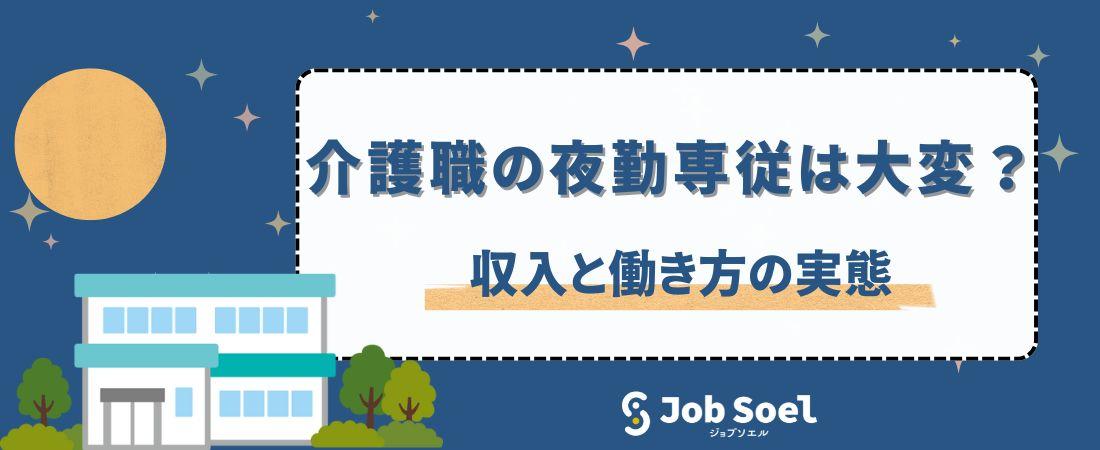
はじめに
介護職にはさまざまな働き方がありますが、その中でも「夜勤専従」は、夜間の勤務だけを専門に担当する働き方です。
「夜勤だけって大変そうだけど、実際はどうなの?」「日勤より稼げるって本当?」「自分にできるのかな?」
そんな疑問を感じている方も多いでしょう。夜勤専従は、生活リズムの調整や体力面、責任感など日勤とは違ったポイントを理解しておくことが大切です。
この記事では、夜勤専従の基本的な働き方、仕事内容、収入の仕組み、メリットと大変さ、確認すべきポイントをまとめました。
これから夜勤専従にチャレンジしてみたい方は、自分に合った働き方を見つけるために、ぜひ参考にしてください。
目次
1. 介護職の夜勤専従とは?
夜勤専従は、日勤や早番・遅番を担当せず、原則として夜勤だけを専門に働くスタイルを指します。主に介護や看護の現場で使われる言葉ですが、事業所によっては研修や会議のために日中の勤務が発生する場合もあります。
施設によって勤務形態は、主に「2交代制」と「3交代制」があります。
2交代制の場合の夜勤は1回あたりの勤務時間が15〜17時間程度と長めで、夕方16〜17時頃から翌朝9〜10時頃まで働くケースが多いです。この場合、1回の夜勤が2労働日に相当するとみなされることが多いため、月の出勤回数は10回程度が一般的です。
一方、3交代制は準夜勤や深夜勤といった1回あたり6〜9時間程度の勤務を複数のスタッフで分担します。例えば、準夜勤が16時〜0時頃、深夜勤が0時〜8時頃というのが一般的な時間帯の一例です。こちらは月に20回程度の勤務が目安です。
施設によっては夜勤専従のスタッフを「週1回だけ」「月に数回だけ」といった少ない回数で募集していることもあります。家庭の事情やWワーク、自分の都合に合わせて夜勤だけ働きたいという理由で、こうしたパート・アルバイトの形を選んでいる人もいます。
不規則な働き方を支えるルール:「変形労働時間制」と「夜勤協定」
夜勤専従は1回の勤務が長時間になることが多いため、労働基準法の「1日8時間・週40時間以内」という原則に合わせて、「変形労働時間制」という仕組みが使われることがあります。
例えば、1回16時間勤務を月10回入る場合でも、1週間あたりの平均労働時間が40時間以内に収まるようにシフトが調整されます。ただし、変形労働時間制は就業規則や労使協定で定める必要があるため、すべての施設に導入されているとは限りません。導入していない場合は、法定労働時間を超えた分は時間外労働として扱われます。
また、大規模な施設などではスタッフの負担が一部に偏らないように、「夜勤協定(夜勤に関する労使協定)」を結んでいるところもあります。
夜勤協定とは、夜勤の回数の上限や1回の夜勤に配置する最低人数などを、スタッフと事業所で話し合い、あらかじめ決めておくルールです。「夜勤協定」は法令用語ではなく、正式には「夜勤に関する労使協定」や「36協定の特例」などの形で締結されることが多いです。
必ずしも協定がないからといって良くない施設というわけではありません。小規模施設やグループホームではスタッフ同士で相談しながら柔軟に夜勤体制を決めている場合もあります。
求人票や面接で、こうした取り決めの有無を確認しておくと安心です。
2. 介護職の夜勤専従の仕事内容とは
夜勤専従の業務は、利用者さんが安全に夜を過ごし、朝を迎えられるようにサポートすることです。
出勤から退勤までの流れの一例を見てみましょう。
【2交代制の例】
2交代制では、夕方に出勤して翌朝まで勤務するのが一般的です。
- 17:00頃に出勤し、日勤スタッフから申し送りを受けます。
- 18:00頃から夕食介助や口腔ケア、服薬介助を行います。
- 21:00頃に消灯後は巡回を開始。巡回では、利用者さんが安全に休めているかを確認し、転倒防止や体調の変化を見逃さないようにします。
- 深夜には排泄介助、体位変換、オムツ交換などを行います。
- 0時前後に仮眠や休憩を取れる時間が設けられていますが、緊急対応があると予定通り取れない場合もあります。
- 早朝6:00頃から起床介助、整容、バイタルチェック(体温や血圧などの確認)、朝食介助を行い、最後に日勤スタッフへ申し送りをして9:00〜10:00頃に退勤します。
【3交代制の深夜勤の例】
3交代制の場合は、勤務時間は一般的に1回6〜9時間ほどです
例えば「準夜勤」は16:00〜0:00頃、「深夜勤」は0:00〜8:00頃など、複数のスタッフが交代で担当します。
- 0:00に出勤し、申し送りを受けた後、1:00頃から巡回や身体介護を行います。
- 3:00頃に短い休憩をはさみ、4:00〜6:00頃に再び巡回や体位変換を行います。
- 6:00以降は起床介助などを担当し、日勤スタッフへ申し送りをして9:00頃に退勤する流れです。
夜勤中は、日勤に多いレクリエーションや入浴介助はほとんどありません。見守り、身体介護、巡回、記録、急変時対応などが中心です。
特に夜間はスタッフの人数が少ない分、一人で判断する場面もあります。そのため、マニュアルの確認とスタッフ同士の連携が欠かせません。
3. 不規則なシフト制より夜勤専従が向いていると感じる人もいます
「夜勤専従は思ったより負担が少ない」と感じる人もいます。
その理由として多いのは、日勤に比べてレクリエーションや入浴介助がなく、身体的負担が軽いことです。夜間は多くの利用者さんが就寝しているため、一定の時間帯は業務が落ち着きやすいのもポイントです。
もちろん巡回や急変対応はありますが、昼間に比べて突発的な対応が少ない時間帯もあります。
また、スタッフの人数が少ないことで人間関係のストレスが軽減されやすいと話す人もいます。日勤のように多職種が出入りする場面が少なく、同じメンバーでの勤務が多いのも理由の一つです。
また、交替勤務のように夜勤と日勤を繰り返すよりも、夜勤専従の方が生活リズムを一定に保ちやすいと感じる人もいます。毎回同じ時間帯に働くことで、体調管理がしやすいと考える方もいるでしょう。
4. 介護職の夜勤専従がきついと感じるポイントは?
一方で、夜勤専従には大変だと感じる面もあります。
まず、2交代制の夜勤は1回の勤務が16時間前後と長時間で、立ち仕事が続くことも多く、体力的な負担は小さくありません。休憩や仮眠が十分に取れないと眠気や集中力の低下につながり、事故やミスのリスクも高まります。
法律上は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩が必要とされていますが、夜勤では突発的な緊急対応などで予定通りに休憩が取れないこともあります。そのため、仮眠室の設備や休憩体制が整っているかどうかは職場選びで確認しておきたいポイントです。
また、昼夜逆転の生活は体調を崩す原因になりやすく、昼間に眠ると音や光の影響で熟睡しにくい人もいます。疲れが残りやすくなるため、自分の生活リズムに合うかどうかを考えることが大切です。
さらに、夜間はスタッフの人数が少ないため、急変など緊急時に一人で判断を迫られるケースもあります。判断力や責任感が求められる分、精神的な負担が大きいと感じる人もいるでしょう。
5. 夜勤専従の介護職の収入と平均の出勤日数
夜勤専従の魅力として、多くの人が気になるのが収入面です。
夜勤には「夜勤手当」と「深夜割増賃金」がつきます。そのため、同じ勤務時間であれば、日勤より高収入が期待できます。
深夜割増は法律で義務づけられていて、22時〜翌5時の深夜労働には基本給の25%以上の割増賃金が必要です。
一方、夜勤手当は法律で義務付けられているわけではなく、各施設が独自に支給しています。金額は職種や施設によって幅があり、数千円〜1万円を超える場合もあります。
例えば2交代制の場合、1回の勤務が2労働日に相当するとみなされることが多く、月10回程度の勤務でもフルタイムと同じくらいの収入を得ている人もいます。
一方で3交代制は1回の勤務時間が8時間前後ですが、深夜割増と夜勤手当を合わせると、日勤より多く稼いでいる人もいます。
最近では、夜勤専従は常勤(正職員)より非常勤(パート・アルバイト)として募集されることが多いのも特徴です。「月2〜4回だけ夜勤に入って副収入を得たい」という人や、Wワークなど自分の都合に合わせて夜勤だけを選ぶ人も増えています。
求人票で夜勤手当ての有無をチェック
求人票で意外と分かりにくいのが、「夜勤手当や深夜割増が時給に含まれているかどうか」です。
例えば「時給1,500円(深夜割増含む)」と書いてあれば、22時〜翌5時の割増がすでに込みの金額なので、追加の深夜手当はありません。
逆に「夜勤手当は別途支給」と明記されていれば、時給とは別に夜勤1回ごとの手当がつくという意味です。
また、手当が「毎回つくのか、月ごとにまとめて支給されるのか」など支給タイミングも施設によって異なります。残業の有無や、夜勤協定があるかどうかも含めて求人票で比較し、求人票にわかりにくい表現があるときは、面接時に必ず確認しておきましょう。
自分は「夜勤専従でも無理なく働けるか」を考える
収入の条件だけでなく、夜勤専従が自分の体力や生活リズムに合うかを考えておくことも大切です。
例えば、長時間勤務や昼夜逆転の生活に慣れる自信があるか、日中の睡眠を家族に妨げられないかをイメージしてみましょう。子育て中の方や家族介護をしている方は、日中の時間をどう確保するかを考えておくと疲労をためにくくなります。
また、副業やWワークを考えている人は、他の仕事と夜勤のスケジュールが無理なく両立できるかを現実的にシミュレーションしてみましょう。
施設によっては、夜勤の人数体制、仮眠室の有無、緊急時の対応マニュアルなどが異なります。面接時には「休憩はどのように取れるのか」「何人で夜勤を回しているのか」など具体的に確認しておくと安心です。
6.実際の夜勤専従求人を見てみるならJobSoelの活用もおすすめ
医療・介護分野での転職には、専門の求人情報プラットフォームであるJobSoel(ジョブソエル)の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
JobSoelでは、全国の医療福祉に関する職種の求人情報を検索できるほか、施設の雰囲気や具体的な取り組みを知ることができます。
新しい職場での働き方や成長のチャンスを具体的にイメージしながら転職活動を進められるので、安心して検討できますよ。
自分に合った職場を見つける一助として、ジョブソエルを活用してみてください。効率的に転職活動を進めるための心強いツールとなるでしょう。
▼求職者様_会員登録ページ
https://jobsoel.com/sign-up
▼企業・法人様_会員登録ページ
https://jobsoel.com/company-sign-up
7.まとめ
夜勤専従は人によって向いている人もいれば、きついと感じる人もいます。
勤務時間や仕事内容、手当の仕組みを正しく理解し、体力や生活リズムと無理なく両立できるかを冷静に考えることが大切です。求人票をしっかり確認し、夜勤の体制や休憩環境、手当の条件まで比べたうえで自分に合った働き方を選びましょう。
