『徘徊』『拒否』『暴言』にどう向き合う? 認知症ケアで迷ったときの基本
いいね
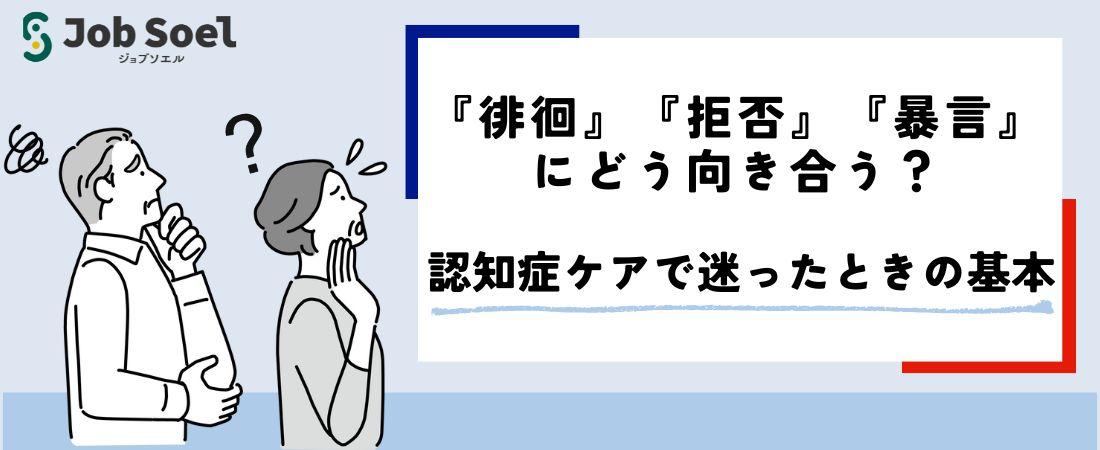
はじめに:
「夜勤中に利用者さまが歩き回っていて、止めるべきか迷った」
「声をかけても反応がなくて、不安になった」
介護の現場では、こうした場面に出会うことが少なくありません。認知症の利用者さまと関わるとき、どう対応すればいいのか迷うのは自然なことです。
認知症ケアは、知識がないと難しく感じられるかもしれません。しかし基本を理解していれば、戸惑いを減らし、利用者さまに寄り添った支援につなげやすくなります。
この記事では、認知症ケアに取り組むうえでまず押さえておきたい基本を整理します。
1. 認知症の基本的な理解
厚生労働省のデータによると、2022年時点で約443万人の高齢者が認知症を患っており、軽度認知障害(MCI)を含めるとおよそ1,000万人にのぼります。これは高齢者の約8人に1人という割合です。
介護職として現場に立てば、認知症の利用者さまと出会うのは特別なことではなく、日常的に起こりうることといえます。
認知症の症状を知っておこう
認知症には大きく二つの症状があります。ひとつは病気そのものによって起こる「中核症状」、もうひとつは環境や心理状態の影響で出てくる「行動・心理症状(BPSD)」です。
中核症状(脳の働きが低下することで起こる症状)
- 記憶障害:新しいことを覚えられない、昔のことが思い出せない
- 記憶障害:見当識障害:時間や場所、人がわからなくなる
- 判断力の低下:複雑な話が理解できない、適切に判断できない
- 実行機能障害:計画を立てて行動することが難しくなる
行動・心理症状(BPSD)
- 心理面:不安、落ち込み、妄想、幻覚など
- 行動面:徘徊、介護拒否、暴言や暴力、不潔行為など
BPSDは必ず出る症状ではありません。環境を整えたり関わり方を工夫したりすることで、予防や軽減ができるといわれています。
認知症の方が感じていること
症状の背景には、その人が抱えている気持ちがあります。例えばこんな思いです。
- 不安や混乱:何が起こっているのかわからない恐怖
- 自尊心の傷つき:できないことが増える悔しさ
- 孤独感:理解してもらえない寂しさ
- 焦燥感:思うようにいかないもどかしさ
こうした気持ちを想像しながら関わることで、ケアの工夫の仕方が変わってきます。
2. 介護現場での対応の基本
パーソン・センタード・ケアの実践
認知症ケアの基本姿勢のひとつが「パーソン・センタード・ケア(Person-Centred Care)」です。これはイギリスの心理学者トム・キットウッドが提唱し、世界的に広く取り入れられている考え方です。
認知症の方を“患者”ではなく“ひとりの人”として尊重し、その人らしさを大切にするケアの基本姿勢です。
接するときに意識したいことは次のような点です。
1.相手の立場に立って考える
- 目線を合わせて話しかける
- 急がず、本人のペースに合わせる
- 失敗を責めず、できたことを褒める
2.声かけの工夫
- 声は低めで、はっきり、ゆっくり
- 複数の指示を同時にせず、一つずつ伝える
- 抽象的ではなく、具体的でわかりやすい言葉を使う
- 「はい・いいえ」だけでなく、選べる質問や開かれた質問を使う
3.環境を整える
- 慣れた場所での支援を優先する
- 大勢で囲まず、落ち着いた雰囲気をつくる
- 集中しやすい時間帯を選ぶ
- 疲れているときは無理に行わない
意思決定支援の基本
厚生労働省の「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」では、認知症の方にも意思があり、意思決定能力を有することを前提とした支援が必要とされています。
意思決定支援のプロセスは次の3つに整理されています。
- 意思形成支援:本人が理解しやすい説明をする
- 意思表明支援:本人の気持ちを丁寧にくみ取る
- 意思実現支援:表明された意思を日常生活に反映させる
3. よくある場面と対応例
徘徊への対応
利用者さまが居室や廊下を何度も歩き回り、止めるべきか迷ったことはありませんか。
徘徊には「家に帰りたい」「探し物をしている」など本人なりの理由があることが多く、ただ制止するだけでは不安を強めてしまうこともあります。
そこで意識したいのは、まず気持ちを理解することです。
- 「どこに行かれるのですか?」と優しく尋ねる
- 強く止めず、一緒に歩いて話を聞く
- 目的がある場合は、その思いを受け止める
ただし、人手が限られていて付き添い続けるのが難しいこともあります。そんなときは安全を優先しながら、自然に切り替えられるよう工夫します。
- 危険のない範囲で歩いてもらう
- 水分補給や休憩を促す
- 疲れたタイミングで別の活動に誘導する
介護拒否への対応
入浴や食事をすすめても「嫌だ」と拒否されるというのはよく起こります。
「なんで受け入れてくれないんだろう」と焦ってしまいますが、理由を探ることが第一歩です。
- 「なぜ嫌なのか」を具体的に聞く
- プライバシーが守られているかを見直す
- タイミングが本人の体調や気分と合っているか確認する
それでも拒否が続くときは、無理に進めず柔軟に切り替えます。
- 時間を変えてみる、職員を変えてみる
- 本人の好みや習慣に合わせて提案する
- 「一緒にやりましょう」と協働の姿勢で関わる
暴言・暴力への対応
突然の暴言や暴力は、介護職にとって心身の負担が大きい場面です。感情的に反応したくなりますが、まずは安全の確保が最優先です。
- 距離を取り、落ち着ける状況をつくる
- 力で対抗しない
- 他の利用者さまの安全を守る
そのうえで、行動の背景に目を向けます。
- 痛みや不快感がないか確認する
- 環境の変化がストレスになっていないか探る
- 状況が続く場合は医師に相談する
声かけの例
✖「やめてください!」
〇「どうされましたか?」
〇「少し休憩しませんか?」
不潔行為への対応
排泄や清潔に関わる行為は、ときに利用者さまの尊厳を大きく揺るがす場面です。焦らず、さりげなく支援する姿勢が求められます。
- 恥ずかしさを与えないように配慮する
- 周囲に見られないよう環境を整える
- 清潔に保ちやすい環境を準備する
繰り返し見られる場合は、根本的な要因を探ります。
- トイレの場所がわからない
- 衣類の着脱が難しい
- 身体の不調や排泄リズムの変化
対応は同じでも、反応は人によって変わります。うまくいかなかった記録も、次の工夫の手がかりになります。
4. 家族やチームとの連携
チームケアの重要性
認知症ケアは一人では担えません。厚生労働省のガイドラインでも「意思決定支援チーム」の重要性が示されています。
医療・介護・家族がそれぞれの視点を持ち寄ることで、利用者さまへの支援をより適切に進めることができます。
効果的なチーム連携を進めるためには、次の工夫が役立ちます。
1.情報共有の徹底
- 日々の様子や小さな変化を記録する
- 成功した対応を共有する
- ケアプランを定期的に見直す
2.専門職との連携
- 医師:進行状況や薬の調整
- ケアマネジャー:サービス調整や家族支援
- 看護師:健康管理や医療的ケア
- 相談員:制度利用や権利擁護
3.家族との協働
- 本人の生活歴や価値観を共有する
- 在宅での様子や変化を聞く
- ケアの方針を一緒に確認する
もちろん、こうした連携が常にスムーズにいくわけではありません。
忙しさの中で記録が後回しになったり、専門職やご家族さまとの意見の食い違いが生じることもあります。そうしたときは、情報を一度整理し直して共有することが改善のきっかけになります。
継続的な支援体制
認知症は時間の経過とともに変化していきます。だからこそ、早い段階から継続して関わる姿勢が必要です。
早期からの継続支援
- 軽度のうちから将来を見据えて準備する
- 本人の意思を確認し続ける
- 状況に応じて対応を変える
記録と振り返り
- 支援の流れや結果を残す
- 定期的に振り返って改善する
- チーム全体で学びを共有する
業務の忙しさの中で、記録や振り返りをすべて完璧にこなすことは難しいものです。少しずつでも続けていくことで、支援の質を積み上げていくことができます。
まとめ:介護職としての想いを大切に
認知症ケアに「唯一の正解」はありません。思いどおりにいかない日もありますが、それは珍しいことではありません。
大切なのは「利用者さまのその人らしさを尊重したい」という気持ちを持ち続けることです。その気持ちがあるからこそ、介護する側の工夫や試行錯誤に意味が生まれます。
今日からできる小さな一歩として、例えばこんな工夫があります。
- 声かけを「◯◯してください」から「一緒にやってみませんか?」に変えてみる
- 記録に「できなかったこと」ではなく「できたこと」を一つ書き残す
- 食事や入浴のときに、まず本人の表情やしぐさを観察してみる
支える側の工夫が増えると、利用者さまが落ち着いて過ごせる時間が増えることに繋がります。
参考:
厚生労働省「認知症及び軽度認知障害の高齢者数と有病率の将来推計」
https://www.mhlw.go.jp/content/001279920.pdf
厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf
厚生労働省 認知症施策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html
