ボーナス3ヶ月分ってどういう意味?“思っていた金額より少ない…”がおこるのはなぜ?
いいね

「〇ヶ月分ってよく聞くけど、何が基準になってるの?」「毎年ちょっとずつ違うのはなぜ?」といった素朴な疑問を抱く方も多いようです。
この記事では、医療・介護・福祉の職場で働く方に向けて、ボーナスの計算のしくみや“基本の考え方”をご紹介します。
目次
1. ボーナスは支給されるのが当たり前…ではないって知っていますか?
ボーナス支給は、実は法律で決まっているわけではない
「ボーナスって、なんとなく夏と冬にあるもの」そんなふうに思っている方も多いのではないでしょうか。周りでも「そろそろボーナス時期だね」なんて会話が出る時期になると、「あ、そういえば私の職場は今年どうなんだろう」と気になってきますよね。
でも実は、ボーナスは“必ず支給されるもの”ではないって、ご存じでしたか?
まず知っておきたいのは、ボーナス(賞与)は法律で支給が決まっているわけではないということ。つまり、会社や法人が「うちは支給しません」と決めていれば、それはルール違反ではないのです。
ボーナス支給の有無は「就業規則」や「給与規定」をチェック
では、ボーナスはどうやって決まるのかというと、多くの場合、職場の「就業規則」や「給与規定」に書かれています。「支給する場合はいつ・どれくらい」「どういった条件で支給対象になるのか」などが明記されていることが多いです。「1年以上勤務した正職員に限る」「支給時点で在籍している人のみ」などの条件がついていることもあります。
ボーナス支給の目的は“成果”への対価や“勤続”への感謝など
ボーナスには「日ごろのがんばりに対する評価」や「長く働いてくれてありがとう」という意味合いが込められているケースが多いです。支給額の決まり方には「勤続年数」「勤務態度」「人事評価」などが影響していることも少なくありません。
つまり、ボーナスは“もらって当たり前”ではなく、職場ごとの方針や評価によって支給されるもの。これを知らずに「いつも一生懸命働いてるのに少ない気がする…」と不満を感じると、なんだか損した気分になりますよね。だからこそ、まずは自分の職場の支給ルールをきちんと知っておくことが大切です。
ちょっと地味な作業かもしれませんが、一度「就業規則」や「給与規定」を見てみるのがおすすめ。意外と知らなかったことが書いてあるかもしれません。
2. よく聞く「ボーナス〇ヶ月分」ってどういう意味?
”基本給”がベースに算出、ただしそれだけではありません
「今年のボーナスは2.0ヶ月分って書いてあったよ」「うちの施設は毎年1.5ヶ月くらいかな」このように、職場で“〇ヶ月分”という表現を耳にすること、ありますよね。でもこの「〇ヶ月分」、いったい何に対しての〇ヶ月なんでしょうか? 月給?手取り?それとも…?
この「〇ヶ月分」、多くの場合は基本給×〇ヶ月という意味で使われています。たとえば「基本給20万円で2ヶ月分なら、40万円支給される」というような計算です。
ちなみにこの“基本給”とは、毎月の給与明細に書かれている金額の中でも、手当などを除いた「基本の部分」を指します。給与明細をよく見ると、「基本給」「処遇改善手当」「夜勤手当」などが分かれて記載されていると思いますが、その「基本給」の欄にある金額がボーナスの計算基準になっていることが多いです。
ただし、これがすべてではありません。実際の支給額には、職能手当や評価による加算、役職手当などがプラスされることもありますし、評価や勤務状況によって調整されるケースもあります。ですので、「〇ヶ月分」と言われても、人によって金額に違いが出てくるのです。
“職能給”や“評価点”がボーナス算定に加わることも
施設によっては、「支給月の基本給×〇ヶ月分」に加えて、職能手当・役職手当・評価点に応じた加算が含まれる場合もあります。たとえば、「基本給は20万円だけど、評価がAだから+2万円」「職能加算が3,000円つく」といった具合です。
また、等級制度がある法人では、同じように勤務していても“等級の違い”によって変わるケースもあります。例えば「等級3以上は+〇円」「等級1は評価が良くても加算なし」などです。
評価による加算方法も様々で、定額で加算する法人もあれば、「係数(倍率)」「評価点数」によって変動させる法人もあります。加算額が毎回同じとは限らず、仕組み自体が公開されていないケースもあります。
求人情報に記載の「賞与:年〇回・〇ヶ月分」とは?
求人情報などに書かれている「賞与:年2回・計4ヶ月分」などの表記は、年間の合計支給額を意味するのが一般的です。
この場合、「夏2ヶ月分+冬2ヶ月分」のように、年2回に分けて支給される合計が4ヶ月分という意味になります。ただし、「夏1.5ヶ月+冬2.5ヶ月」や「冬のみ支給」といった内訳の場合もあり、実際の回数や時期、支給条件は就業規則や給与規定を確認しないとわからないことも多いです。
ボーナス支給額の計算例:実際どうなる?
たとえば、年間で「年2回・計4ヶ月分(夏2ヶ月+冬2ヶ月)」のボーナス支給がある職場で、今回が夏のボーナス(2ヶ月分)だったとしましょう。
このときの支給額は以下のようになります:
- 基本給:20万円
- 支給月数:2ヶ月分
- 職能手当:1万円
- 評価加算:5,000円
→ 支給額合計:20万円×2ヶ月=40万円+1万円+5,000円=41万5,000円
逆に、欠勤などがあり評価が低かった場合などには、加算がつかず支給額が下がるケースもあります。
3. ボーナスの額面と手取り額、なぜこんなに引かれるの?手取りが減る理由
ボーナスの手取り、思ったより少なくてがっかり…そんな経験、ありませんか?
「手取り20万円くらいあるかなと思ったら、17万円ちょっとだった…」
ボーナスの明細を見て、そんなふうに思った経験はありませんか?期待していた額と比べて手取りがずいぶん少なく感じて、「こんなに引かれるの!?」と驚く方も少なくありません。
ですが、これは損をしているわけではなく、きちんと法律や制度に基づいて計算された結果です。ここでは、ボーナスから引かれる主な項目と、その理由を確認してみましょう。
ボーナスからは所得税と社会保険料が引かれる
まず、ボーナスからは「所得税」と「社会保険料」が差し引かれます。
【所得税】
賞与にかかる所得税は、「賞与に対する算出税額の算出方法」によって源泉徴収されます。
この方法では、以下の2つの情報をもとに、国税庁の定めた税額表に照らして計算されます
- 前月の社会保険料控除後の給与額
- 扶養している家族(扶養親族等)の人数
つまり、一律の税率(定率)で計算されているわけではなく、人によって税額が異なるのが特徴です。これにより、「思っていたより引かれた」と感じやすい要因のひとつになっています。
【社会保険料】
加えて、ボーナスにも以下の社会保険料がかかります:
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 介護保険料(40歳以上の場合)
ボーナスは“臨時収入”のように感じられるかもしれませんが、これらの保険料の対象に含まれるため、通常の給与と同じように控除されるのが基本です。
【住民税は通常ボーナスからは引かれない】
住民税は、基本的に前年度の所得をもとに計算された年額を、12ヶ月に分けて毎月の給与から天引きされる仕組みになっています。そのため、ボーナス(賞与)からは住民税が控除されないのが一般的です。ただし、年末調整や住民税の清算などが関係する例外的なケースもあり、給与明細の確認は大切です。
引かれる控除額は人によって違います
もうひとつ見落としがちなのが、引かれる額は人によって違うということです。
「同じような金額のボーナスなのに、手取りがあの人と違う…」と感じたことがある方もいるかもしれません。これは、以下のような個人の条件によって控除額が異なるためです。
- 扶養している家族の人数
- 加入している保険の種類(介護保険の有無など)
- 前月の給与額(所得税の源泉徴収に影響)
そのため、同じ支給額でも手取りが微妙に違うことがあるのは、こうした条件の差によるものです。
「なんだか自分だけ少ない気がする…」と思っても、それは損しているのではなく、その人の状況に応じて計算された結果です。
明細や源泉徴収票を見ると、「何にどのくらい引かれているのか」が書かれています。ですが、たとえ理由がわかっても「こんなに引かれるのかぁ…」という気持ちは、やっぱり出てきてしまうかもしれませんね。
4. 私だけボーナス支給額が少ないかも?ボーナス支給額の“差”がつく理由は?
同じ職場なのに、なんで…?
「同期より少なかった」「なんとなくあの人のほうが多そう」
ボーナスの話って、なかなか面と向かっては聞けないもの。でも、支給額の雰囲気や会話の端々から、「もしかして自分だけ少ない?」と感じたことがある方もいるかもしれません。
とくに、業務内容やシフトが似ている同僚と比べて金額に差があるように思えると、その理由が気になることもあるでしょう。
評価・勤続年数・査定期間が関係
ボーナスの金額は、単純に「月給×〇ヶ月」で決まるわけではありません。多くの場合、複数の要素をもとに算出されています。
例えば
- 勤続年数
施設によっては「1年以上勤務していないと減額」といったルールがあることも。たとえ同期でも、入職日が数週間違うだけで支給額に差が出る場合があります。 - 等級や役職の違い
「主任以上は+0.5ヶ月分支給」など、役職に応じた加算を設けている法人もあります。また、等級制度がある職場では、「等級2は+3,000円、等級3は+8,000円」といった形で、職能給が加算されるケースもあります。 - 勤務状況(勤怠)
査定期間中の欠勤・遅刻・早退、あるいは休職などが影響する場合もあります。出勤日数や勤務時間が一定の基準を下回ると、ボーナスに反映されることもあります - 人事評価の基準
「協調性」「責任感」「技術力」など、具体的な評価項目が点数化されている職場では、本人が意識していない細かな基準で差がつくこともあります。たとえば、「スキル面は高評価でも、勤務態度の項目で点数が下がっていた」といったようなケースです。
これらの要素を総合して、最終的な支給額が決まる仕組みです。とくに評価制度が明確でない職場では、支給額の差に気づいても、納得しづらいことがあります。
ボーナス支給額に納得がいかないとき、どこを見ればいい?
「何を見てそう評価されたのかがわからない」「点数の理由が説明されない」と感じる場合は、評価の根拠を確認できる資料に目を通してみるのもひとつの手です。
こうした評価制度や支給基準は、法人ごとに運用ルールが大きく異なるため、他の職場と単純に比較することはできません。
支給額の計算方法や評価のルールは、就業規則や評価項目一覧などに記載されていることがあります。評価点や金額だけで判断すると背景が見えにくいこともありますが、何を基準にしているかが理解できれば、自分の評価や支給額の理由を整理しやすくなります。
5. ボーナス支給後に考える人も多い?退職を見据えた準備とは
「ボーナスが出たら退職しようと思っている」という話を耳にしたことがある方もいるかもしれません。実際、ボーナス支給のタイミングを一区切りとして、転職や退職を検討する人は少なくありません。これまでがんばってきた自分に区切りをつけて、新しいスタートを切るにはちょうどいいタイミングでもあります。
とはいえ、退職には意外と手間がかかるものです。手続きや引き継ぎ、失業保険の準備など、スムーズに進めるには早めの情報収集が欠かせません。
6.転職活動とJobSoel(ジョブソエル)の活用
「このままでいいのかな」「もっと自分に合った職場はないかな」と思ったときは、少しずつ次のステップに目を向けてみるのもひとつの方法です。
転職先を探す際には、仕事内容だけでなく、ボーナスの支給実績や人事評価のしくみなども気になるポイントですよね。
医療・介護分野での転職には、専門の求人情報プラットフォームであるJobSoel(ジョブソエル)の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
JobSoelでは、全国の医療福祉に関する職種の求人情報を検索できるほか、施設の雰囲気や具体的な取り組みを知ることができます。
新しい職場での働き方や成長のチャンスを具体的にイメージしながら転職活動を進められるので、安心して検討できますよ。
自分に合った職場を見つける一助として、ジョブソエルを活用してみてください。効率的に転職活動を進めるための心強いツールとなるでしょう。
▼求職者様_会員登録ページ
https://jobsoel.com/sign-up
▼企業・法人様_会員登録ページ
https://jobsoel.com/company-sign-up
あわせて読みたい

介護職へ転職する前に!
施設見学で後悔しない5つのポイント
7.まとめ
ボーナスの金額には、勤続年数や役職、勤務状況、人事評価など、さまざまな要素が関係しています。
「〇ヶ月分」と聞くと一見シンプルに思えますが、実際は個人ごとの条件が反映された結果であることがわかります。
もし「どうして自分はこの金額なんだろう?」と感じたときは、まずは評価制度や給与規定を確認してみるのがおすすめです。自分の状況を客観的に整理できると、見え方も少しずつ変わってくるかもしれません。
もちろん、「知ったからといってすぐ納得できる」とは限りません。ですが、自分の働き方やこれからのキャリアを見つめ直すひとつのきっかけにはなるはずです。
ボーナスは、日々のがんばりを振り返る節目でもあり、「これからどう働くか」を考えるタイミングでもあります。
今の職場にとどまるのか、次のステップに進むのか、じっくり向き合う材料のひとつとして、今回の内容を活かしていただけたら嬉しいです。

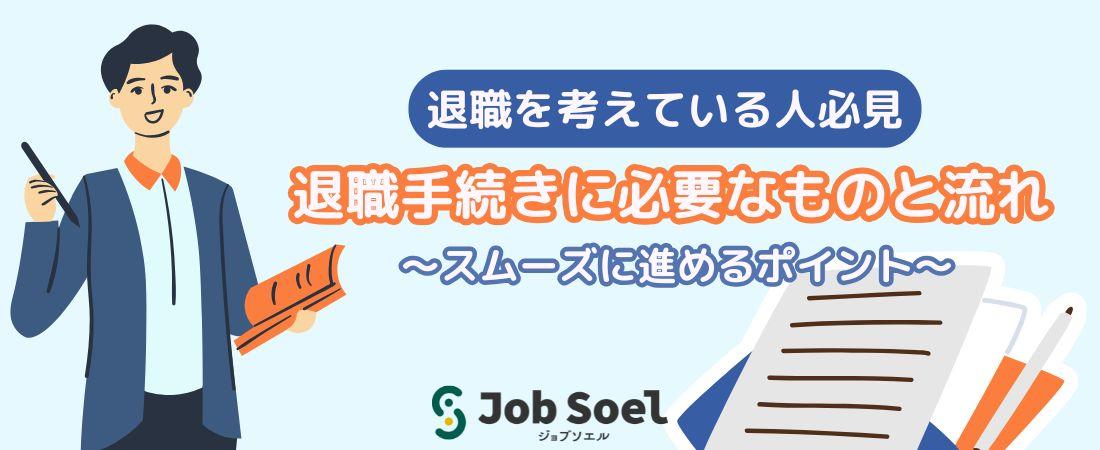
.jpg)